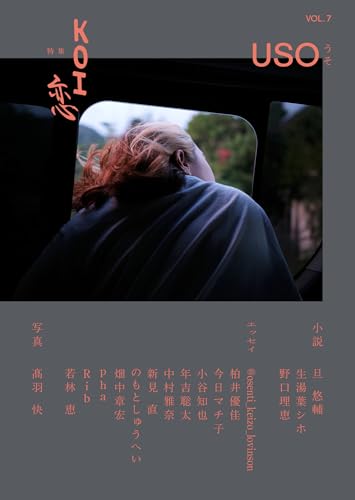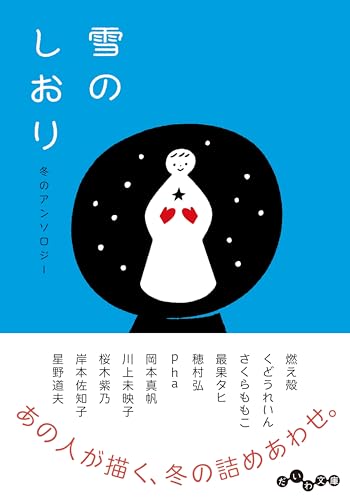・著書 → Amazon.co.jp | pha
・note → phaのnote
・Twitter → @pha
・メール → pha.japan@gmail.com
『毎日酒を飲みながらゲーム実況してたら膵臓が爆発して何度も死にかけた話』のたろちんさんと対談しました
『毎日酒を飲みながらゲーム実況してたら膵臓が爆発して何度も死にかけた話』はタイトル通りの話なのですが、とても面白かったです。自分の身に起こった事態をなんだか外側から実況しているような感じがあって、なので深刻な話なのに笑いながら読めてしまう。文章が上手くてグイグイ読まされてしまう。ネット的な文体ではあるんだけど、本として読んでも違和感のない感じですね。
面白く読んだあとで、人生について考えさせられてしまいますね。膵臓が爆発してもうお酒を飲めなくなってしまったたろちんさんだけど、「あの頃お酒を飲んでいたのは自分に必要だった」というようなことを言っていて、そういうことってあるよな、と思います。僕も、あの頃はああしかできなかったんだよな、ということがいくつもありますね。
パーティーが終わったあとにどう生きていくか、考え続けないといけないな……。
2024・2025年に発表した短歌まとめ
最近はあまり作ってないんですが、ここ数年で発表した短歌がいくつかあるので、散逸しないようにまとめておきます。
2024年
『ねむらない樹 vol.11 』
春休み
珍しく午前に起きて噛み切ったベーグルが恐竜に似るまで
腰や腰以外の部所をかばいつつ駅前で聴く吹奏楽部
いつまでも覚えられない祝日がいつの間にかなくなっていた
それ以外名前を知らないかのように桜の木だと何度でも言う
お通しの茄子が美味しい居酒屋は浄土みたいな提灯だらけ
クーポンはあしたの24時まででコブサラダのコブって何だっけ
春休みみたいな名前の由来をお湯がわいたら訊ねてみよう
『短歌研究 2024年 5+6月号』
伸びていく
誰も見ていないときにはゆっくりと落ちる椿の花 繰り返す
駅前で俯いている男性が摂取していた液体と串
蛇のように水のホースが跳ねまわる夏にあなたがぐんぐん伸びる
人間が食べやすいよう長くした小麦を麺という──着丼
腰を下ろして中身を出してなんだっけ、ああそうだ、流すんだ全てを
『胎動短歌 Collective vol.5』
なめらかさ
曲がり角の向こうに蝉がいてそれが死んでいたという記憶がある
あのひともあのひとも疎遠になって 夜中に耳をなでまわす癖
向こう側にたどりついたらどうでもいい写真を撮って送るよ、道とか
少しだけ涼しい それに それだから わかってないって言われるんだろう
有料の展望台から見えるものすべてを点と線に変えても
ワックスをつける ワックスをとる 細かい砂にまみれていたい
一度溶けて凍った氷特有のなめらかさを覚えたまま生きる
どの歌も嫌いでどの歌も良くてバッグに入るだけ詰め込んだ
2025年
『短歌研究 2025年 5+6月号』
UNKNOWN
人生はスゴロクみたいなものだって思っていたらこうなりました
すり減っていくだけだからとりあえず注文をしなくては だめだ
戻るならどの瞬間に冬にまだ普通に生活できてた頃に
コンビニができてつぶれてそのあともいろいろあってもうわからない
犬などが近寄ってこない こんな日は月が欠けてるんだろう 眠い
大昔の子どもが空き地に集まって遊んだのは嘘かもしれないね
コンビニができてつぶれて もうわからない
カクヨムコンテスト11の募集が始まりました
2月2日まで。僕は短編のエッセイ部門の審査員をしているので、なんか書いて送ってください!
インタビューでエッセイの書き方について話したので、よかったら読んでください。
穂村弘さん、小島なおさんと短歌トークをしてきました
『短歌のガチャポン、もう一回』に歌を引いてもらった流れでいろいろ話してきました。短歌について話すのはとても楽しい。もっとこういう仕事をやっていきたいですね。
『季刊日記 創刊号』で植本一子さんと対談しました
なんだか日記がちょっとブームになっているらしく、日記だけの文芸誌というものが登場しました。いろんな人たちが日記を書いたり、日記について語ったりしています。
日記といえばこの人、という写真家の植本一子さんと対談しています。日記を書くことや、それを自分で本にして売ることについて、いろいろ語っています。日記は商業出版よりも、手作りで売るのが似合いますね。
あと、個人的に日記に関する本を書いていて、来春くらいに出る予定です。
『USO7』に「平気でうそをつけたら」というエッセイを書きました
「あなたの嘘を教えてください」というテーマで、さまざまな作家が書き下ろす文芸誌シリーズ、「USO」にエッセイを寄稿しました。
好きな雑誌なのでうれしいです。みんな適当な嘘を書いているのかと思ったら、ヒリヒリするような本当のこと(っぽいこと)ばかりが書いてあったりします。
『USO』は主催者の野口理恵さんが先陣を切って、身を切るようなことを書いているので、自分も書かなければ、という気持ちにさせられるんですよね。他では書けないこともここでは書ける、という心理的安全性がある場所だな、と思いました。『USO』に書いた文章をまとめた野口さんの本もとてもよかったです。
『雪のしおり』というエッセイアンソロジーに「冬とカモメとフィッシュマンズ」を収録していただきました
いろいろな作家の冬に関するエッセイを集めたアンソロジーです。豪華メンツに混ぜてもらえてうれしい。
僕は京都で何もできないままフィッシュマンズばかり聴いていた頃のことを書いています。